障害児支援における今回の報酬改定において、特に大きなポイントと言えるのは、以下の2つと考えます。
①5領域を全て含めた総合的な支援の提供
こどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、全ての事業所に対して、支援において、5領域すべてを含めた総合的な支援を提供することが運営基準に明記されました。支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める内容となっています。
5領域とは、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」を指します。

5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算措置も設けられています。ただし、この措置には、令和7年4月1日までの猶予期間があります。
②区分1〜3の時間区分への変更
支援時間による区分が設定され、30分未満の支援は算定不可となりました。
その他、様々な新しい加算が制度化されました。この状況を踏まえて、この改定後の事業所運営で特に重要だと考えられるのは、以下の2点です。
それは・・・、
①事務作業の効率化!!
⇨5領域・・・時間区分・・・連携加算・・・等々
特に、児発管に係る負担が増大の恐れ
特に児童発達管理責任者にとって、今回の改定によっての事務作業の負担は増大していると思います。5領域に根差した個別支援計画の作成や、新たな加算が増えて、これに対する対応やエビデンスの保管などに追われてしまう恐れがあります。
児発管の負担が増えれば、残業の増加、結果として他の職員への目配りがいかず、離職などに繋がることも考えられます。そうなって困るのは、子どもとその保護者、関係者の皆さまです。
そうした状況にならないよう、事務作業の効率化のための仕組みづくりを急ぐ必要があります。
②戦略を立てて加算を取得する!!
⇨「どんな加算も取れるなら取る」という姿勢は、工数負けになる恐れあ
り。狙う加算を絞って効率も重視!!
今回の改正で新たに加算が増えました。たとえば、「自立サポート加算(高校生(2・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行なった場合)や「通所自立支援加算(学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行なった場合)」など、今まで意識の高い事業所が取り組んできた内容が、加算として評価されるようになりました。
ただ、「どんな加算も取れるなら取る」というスタンスで色々な加算に手を伸ばすことは、いたずらに事務作業の増大を招きかねません。加算も、内容によってはそこまでの売り上げ増に繋がるわけではなく、頑張って取得したはいいけれど、工数負けとなってしまう可能性もあります。
狙う加算を戦略的に絞って取り組むことで、効率につながり、結果としてそれが各教室の強みとなっていきます。
戦略を立てて加算を取得するのも、今回の報酬改定で非常に重要な視点です。
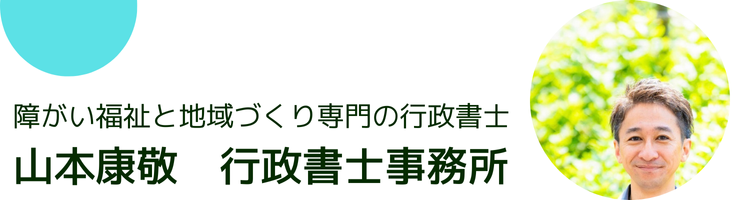


コメント