私は、公務員時代の後半は、障がい福祉と子育て支援を中心とした地域づくりのための仕掛けづくりに尽力してきました。
いくつか例を挙げますが、これらの経験を活かし、これからは地域側から地域づくりの本質に関わっていきたいと思っています。その際は、行政機関との連携も必要となりますので、地域と行政の橋渡し役的な立ち位置で地域の皆様と一緒に取り組んでいきたいと考えています。
巡回支援専門員整備事業の実施
巡回支援専門員整備事業とは、障がい児の福祉の向上を図ることを目的に、保育所や幼稚園、小中学校や放課後児童クラブなどを保育士や臨床心理士などの専門職員が巡回し、発達障がいの早期発見や早期支援を行うための事業です。
本事業は、事業所への委託事業として実施する市町村がほとんどですが、当時は本事業の実施に理解のある事業者が少なかったという理由もありますが、何よりも的確に町民ニーズを把握し、意義のある事業とするために、直営実施手法を取って体制を整備しました。そのために、本事業を実施するための専門職員(保育士、臨床心理士、精神保健福祉士、言語聴覚士、作業療法士)を直接雇用しました。
こころの相談事業の実施
精神保健福祉士及び臨床心理士を正規職員として雇用の上、障がい児支援に留まらず、すべての世代に対する支援を可能とする事業を考えました。
この「こころの相談事業」は、メンタルヘルスに悩みのある方とその家族に対する、いわばよろず相談的なものであり、町の職員である専門職員が直接町民の相談を聞くことで、町民の心の健康の保持増進に資するともに、町民ニーズの把握にも一役かう重要な事業となりました。
障がい者基幹相談支援センターの設置
熊本県内の町レベルでは初となる「障がい者基幹相談支援センター」を、令和3年度に役場福祉課内に設置しました。
相談を軸とした地域生活支援拠点を面的整備で整備するに当たり、基幹相談支援センターの設置は必須でした。
基幹相談支援センターを設置したことにより、地域の相談支援の拠点として重層的な相談支援体制の整備ができました。
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
俗に「にも包括」と言われます。
平成18年に障害者自立支援法が施行され、それまでのいわゆる支援費制度では支援の対象外であった精神障がいも、身体・知的障がいと同様に支援の対象となったことは、画期的な改革であったと思います。
しかし、今現在もなお、精神障がいに対する理解は、他の障がいと比べて進んでいるとは言い難いと私は思っています。ちなみに発達障がいは、精神障がいの部類に含められています。
「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」を構築することは、現在は市町村の障害福祉計画の成果目標にも位置付けられています。
しかし、行政のシステムって、当事者不在であることが多いと思います。
私は、行政時代にこのシステム構築にも大きく関わりました。具体的には、行政主導によるシステム構築から官民連携によるシステム構築へとシフトし、地域の事業所と協働しつつ、当事者も参画するシステム構築を実現しました。
こども総合相談室の設置
児童福祉法の改正により、令和6年度から「こども家庭センター」の設置が市町村に義務付けられました。(努力義務)。
私が在籍していた菊陽町でも、令和6年4月1日付けでこども家庭センターが設置されましたが、これに先立ち、菊陽町では令和3年10月から「こども総合相談室」を開設しています。この「こども総合相談室」のコンセプトは、
- 子どもとその保護者に関わる相談であれば何でも受け付け、相談から支援までワンストップで対応する(相談の吸い上げ機能)
- 相談内容を精査し、適切に関係課(機関)へつなぐ
- 複合的な問題を抱える困難ケースについては、ケース情報を整理の上、必要に応じて関係課等を召集し、ケース会議を開催する(ケースについてのコーディネートをする空間/学校単独では支援が困難な複合化・複雑化したケースに対応するため、福祉と教育の更なる連携強化)
- 定期的な情報共有の場(更なる専門性の向上を図る/コーディネート機能の向上(ブラッシュアップ)を図る)
でした。
ポイントは、教育と福祉の連携強化という点です。学齢期への移行支援とその後と支援は意外になおざりにされてしまいがちだと思います。0歳から18歳まで、さらにその後の支援もにらんだ体制整備に尽力しました。
地域共生社会とは??
地域共生社会とは、地域住民や地域の多様な主体が分野や属性の壁を越えてつながり、誰もが支え合う地域をつくって行くことを目指すものです。
日本では、公的な支援制度が整備されるよりも前から、地域の相互扶助や家族同士の助け合いが行われてきました。
しかし現代では、都市部への人の移動や、個人主義化や核家族化、共働き世帯の増加などの社会の変化に伴って、地域や家庭が果たしてきた役割の一部を補完・代替する必要性が高まっています。
そこで、国では、社会保障制度という形で、疾病や障がい・介護・育児・子育てといった人生において典型的なリスクや課題を想定した現金給付や福祉サービスといった属性別・対象者のリスク別の公的支援を拡充してきました。
一方で、個人が抱える生きづらさや、リスクが複雑化・複合化してきた中で、従来の縦割りの公的支援の仕組みではケアしきれないケースが発生し出します。例えば、
- 育児と介護のダブルケアに直面する世帯
- 障がいのある子の親が要介護状態になった世帯
- 病気の治療と就労の両立をしている方
- メンタルヘルスに課題を抱えながら子どもの養育をしている方
- 刑務所からの出所後に孤立して生活困窮などを抱えている方
- さまざまな背景をもってひきこもり状態にある方やその家族
また、このような公的支援の課題に加えて、「社会的孤立」の問題や、制度が対象としないようなゴミ出し・買い物・通院などの身近な生活課題や、軽度の認知症や精神障がい等が疑われるものの公的支援の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題といった課題も顕在化しています。
このような新たな課題に対応するためには、「その人の生活を支えるために何が必要か」という本人主体の観点を重視することが必要となります。また、複雑化・複合化した課題は何も特別なものではなく、いつでも、誰にでも起こりうるものであり、行政や福祉支援機関のみならず、地域住民一人ひとりが自分ごととして、支え合う地域づくりに参画していくことが求められます。
そこで、「支える側」「支えられる側」という一方向の関係ではなく、「地域に生きて暮らしている以上、誰もが支え・支えられるものである」という考えのもと、地域の資源や人の多様性を活かしながら、人と人、人と社会がつながり合う取り組みが生まれやすいような環境を整えることを目指し、「地域共生社会」というコンセプトが掲げられるようになりました。

私は、これまでの行政機関での経験を活かし、地域共生社会の実現に向けて、地域住民の皆さま、関係機関の皆さま、行政機関の皆さまと一緒になって汗をかきたいと思っています。
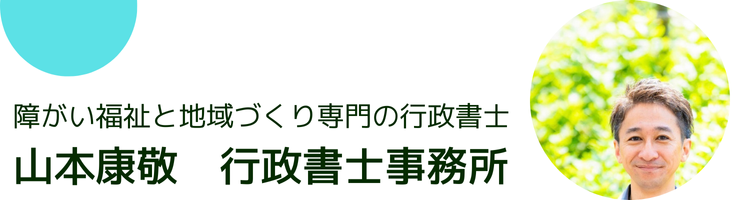


コメント